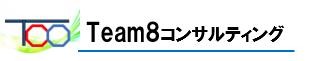ここで説明する理論は、イノベーション研究に大きな影響を与えたジェームス・マーチの1991年の論文「Exploration and exploitation in organizational learning」(組織学習における知の探索と知の深化)で説明されている「組織学習」の理論である。
組織学習(イノベーションも含まれる)理論の多くは、認知心理学に基礎をおき「カーネギー学派」の影響を大きく受けている。
組織学習の定義
組織学習とは、「経験の関数」として生じる「組織の知の変化」と定義できることに、ほとんどの研究者は賛同するだろう。(Argote,2011,p.1124. 入山章栄 訳)
上記定義は、カーネギーメロン大学のリンダ・アルゴーティが2011年に「オーガニゼーション・サイエンス」に発表した論文の一部である。
組織学習の循環プロセスを図表で掲載する。

(世界標準の経営理論 p225 図表1を掲載)
サブプロセス① 組織・人・ツール→経験
組織・人の「限定された合理性」を前提とし、限られた認知を拡げるためにサーチを行う。サーチを行った結果、経験を得ることができる。
サブプロセス② 経験→知
組織は、その経験を通じて、新たな知を獲得する。知の獲得には大きく3つのルートがある。
知の創造:経験で得た知と、自身が既に持っている既存知を組合せ、新しい知を生み出す。
知の移転:人・組織は自ら知を生み出さなくても、外部から知を手に入れることができる。(例 技術提携など)
代理経験:他者の経験を観察することことから知を獲得する。(例 先行者の観察など)
サブプロセス③ 知→人・組織・ツール
「組織の記憶」と呼ばれる。新しく生み出された知は、何らかの形で組織に記憶される。「組織の記憶」のプロセスは「知の保存」と「知の引き出し」に分類することができる。
「知の探索」と「知の深化」
図表1「組織学習の循環プロセス」のサブプロセス①にあたるサーチが「知の探索」である。サーチとは「自身の認知の範囲の外に出ること」である。人や組織には「限定された合理性」があるため、本当はもっと有益な選択肢があるにもかかわらず、認識ができない。したがって「サーチ」することで認知の範囲を広げる必要がある。このサーチという概念を発展させ、「知の探索」を提示し、その対立概念である「知の深化」も提示することで、探索と深化のバランスの重要性を検証したのがスタンフォード大学のジェームズ・マーチの1991年の論文である。
「知の探索」の定義
- 知の探索とは、「サーチ」「変化」「リスク・テイキング」「実験」「遊び」「柔軟性」「発見」「イノベーション」といった言葉でとらえられるものを内包する。(March,1991,p.71. 入山章栄氏 意訳)
- 知の探索とは、これから来るかもしれない「新しい知の追求」である(levinthal&March,1993p.105. 入山章栄氏 意訳)
- 知の探索とは、組織の知の基盤(と技術)からの逸脱である。(Lavie et al.,2010,p.114より抜粋 入山章栄氏 意訳)
「知の深化」の定義
- 知の深化とは、「精錬」「選択」「生産」「効率」「選択」「導入」「実行」といった言葉でとらえられるものを内包する。(March,1991,p.71. 入山章栄氏 意訳)
- 知の深化とは、「すでに知っていることの活用である」である。(levinthal&March,1993p.105. 入山章栄氏 意訳)
- 知の深化とは、組織に既に存在している知の基盤に基づいたものに関連している。(Lavie et al.,2010,p.114より抜粋 入山章栄氏 意訳)
両利きの経営
知の探索・知の深化の理論がイノベーションに重要と言われる。人や組織の認知に限界があるため「いま認知できている目の前の知同士だけ」を組み合わせる傾向がある。そして、時間が経過すると、新しい知が生まれなくなる。だから、「自分の現在の認知の範囲外にある知を探索し、それを今自分の持っている知と新しく組み合わせること」が大切になる。
知の探索は、新しいビジネスの種を探すこと、知の深化は、その新しいビジネスを具現化し、磨きをかけ自社の収益事業にすること。この2つがバランスよく行われる経営を「両利きの経営」と呼んでいる。
しかし、「知の探索」は時間とコストがかるため長続きしない、その結果、集中と選択などの耳障りの良い言葉とともに、「知の深化」に偏っていく。結果として中長期的なイノベーションが枯渇していき、自己破壊していく。この現象をコンピテンシートラップという。
両利きの経営の実践例
1991年以降、知の探索・知の深化の理論の実証研究は、戦略レベル、組織レベル・個人レベル行われてきた。下記にそれぞれの実践例を列記し簡単な説明を行う。
ここで重要なのは戦略・組織・個人のすべてで実践できるということである。
戦略レベル
- オープンイノベーション戦略:技術提携やアライアンス
- コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC投資):大企業がスタートアップ企業に出資し、大企業の販路で市場開拓をする。又は、大企業が、スタートアップ企業に資金と人材を送り出し、大企業の人材に知の探索を経験させる。など
組織レベル
- 出島(知の探索)部門を設置する:独立性を持たせ、意思決定ルールや評価制度を既存のそれから切り離さなければ失敗する。
- 人材の多様化(ダイバーシティ)を取り入れる:「タスク型の多様性」と「デモグラフィー型の多様性」があり、タスク型の多様性は組織パフォーマンスにプラスの影響を及ぼす。デモグラフィー型(性別、国籍、人種、年齢)の多様性を組織に単純に取り入れると、組織のパフォーマンスにプラスの影響を及ぼさず、かえってマイナスの影響を与えることがある。組織内にイングループ・バイアス(認知バイアスグループ)ができないように編成をすることが重要である。
個人レベル
イントラパーソナル・ダイバーシティ:多様な経験を積んでいる個人。副業の容認。