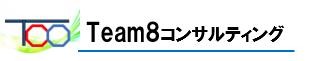カーネギー学派の「人・組織には認知の限界がある」の影響を受けた進化理論である。
人・組織は「限られた選択肢」→「実行によるサーチ」→「認知の拡大」といったプロセスを土台として、「ルーティン」という概念を用い、組織の進化理論に発展させている。
ルーティンとは
入山章栄氏の定義(世界標準の経営理論2019,p.287)
ルーティンとは「組織のメンバーが同じ行動を繰り返すことで共有する、暗黙知と形式知を土台にした行動プロセスのパターン」である。
では、組織の進化になぜルーティンが必要であるかというと、組織にの認知キャパシティに余裕を生み出し、新たに認知の幅を広げるためにルーティンとして組織の中に「知を埋め込む」必要があるからである。具体的には、工場での5S運動に基づく行動、徹底的に使いこなされている業務管理システムとその運用ノウハウなどがルーティンにあたる。
ルーティンが組織にもたらす効果
マーカス・ベッカー2004年の論文にルーティンの効果が述べられている。
安定化
ルーティン化により組織メンバーが繰り返し行う業務や行動プロセスは平準化され、予見や比較がしやすくなるためマネジメントが行いやすくなる。また、メンバー間の仕事の目線がが揃うので、コミュニケーション効率が上がる。
記憶
ルーティンは組織に知を埋め込むメカニズムである。シェアード・メンタル・モデル(SMM)やトランザクティブ・メモリー・システム(TMS)と並ぶ組織の記憶の仕組みである。違いはSMMやTMSは「形式知」を主に引き出すメカニズムであるのに対し、ルーティンはノウハウなどの「暗黙知」の保存を強調している。
進化
ルーティンの充実した組織は、認知キャパシティに余裕が生まれ、サーチ、行動がしやすくなり、新たな知を受け入れられるようになる。結果として、組織の認知の幅を広げ、そこから学習し、進化できるようになる。
ルーティン化の特性
ルーティン化していくことの特性について説明する
少しづつ変化する
以前に形成されたルーティンに許容されて、新たなルーティンに進化する。サーチによって新たに得た知を内部に埋め込むためには、組織に許容力が求められる。ルーティンが多様で広範な知を受け入れられる能力を「吸収能力」という。
経路依存性
一度築いたルーティンの方向性を、急激に大幅に変えることは難しい。ルーティンができあがった経緯によって、進化の方向性は制約を受ける。これを「経路依存性」という。
硬直化
安定化が行きすぎ、経路依存性が強くなりすぎると、組織はサーチを行わなくなり、外からの知を受け付けなくなる。よってルーティンは硬直化し、組織の進化が止まることになる。
硬直化への留意点
- メンバー変更、体制見直しによりルーティンの進化を意識する
- リソースの配置は柔軟にできても、ルーティンが硬直していることを意識する
- 新しい事業には、新しいルーティンを作ることを意識する