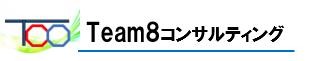そもそも「働く人」をどのような「人間観」で捉えるか?
ここ2カ月くらいの間、人材の定着にかかわる課題について考え、人前で話す機会が多くありました。
早期離職の理由
人材が職場から離れてしまう理由について、人材系の民間企業がさまざまなアンケート調査を行ったものがあり、その結果も公開されています。
リクルートマネジメントソリューションズの実施した「2023年新人・若手の早期離職に関する実態調査」によると、「労働環境・条件がよくない」、「給与水準に満足できない」が上位であり、その次にくる理由が「職場の人間関係がよくない、合わない」「上司と合わない」、退職には至っていないものの、辞めたいと思った理由のトップは、「仕事にやりがい・意義を感じない」なのです。

その退職理由から対策は打てますか?
公開されているよく似たアンケート結果も、少し極端に要約すると社会経済環境の変化、働く人の価値観の多様化、若者世代の価値観とのミスマッチなどで片付けようとしています。
これを中小企業の経営者や人事担当者が知ったところで、一体何の手が打てるのでしょうか?
確かに社会経済環境の変化の中で、働き方改革、ワークライフバランス、そして賃上げの推進に対応するための年間休日の増加、残業削減や賃金水準の見直しは具体的に取り組むことは可能です。
しかし、職場の人間関係や仕事のやりがい・意義など主観的な要因ついては、何を道標として取組みや施策を考えればよいのでしょうか?それが、私のモヤモヤであり、模索していることでもあります。
「アドラー心理学」からの示唆
この模索の中で私が有益な示唆を受けているのが「アドラー心理学」なのです。
「アドラー心理学」が知られたのは古賀史健・岸見一郎共著の「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」が出版されてからです。私もそのタイミングでアドラー心理学の考え方を知り、気になった時に読み直す程度でしたが、最近「アドラー心理学」に関連する書籍を数冊読み、さらに知見を深めているところです。
アドラー心理学は、「個人(その人全部)を理解するための心理学」「自己啓発の源流」と呼ばれていることもあり、「人間とはなにか」「人間関係とはなにか」「劣等感と優越感」など、社会(組織)の中で働く人を理解する上で、腑に落ちる考え方がたくさんあることに気が付きました。

「人間観」を定義してみる
では、アドラー心理学は、人間をどのように捉えているかを、私の主観が含まれていますが箇条書きにしてみます。
- 人は皆、「劣等感(人より劣っているという感情)」を持っている。
- 正しい「劣等感」は、正しい目的となり成長のエネルギーになる。
- 成長の正しい目的を見つけられないと、「劣等感」は「劣等コンプレックス」に変質する。
- 「劣等コンプレックス」から逃げたいという欲求は、逆に、コンプレックスを悟られまいと思い、虚栄心(優越コンプレックス)を生み出す。
- 「劣等コンプレックス」から逃げ続けるために、虚栄、怒り、悲観、自虐、閉じこもりなどの感情を使い、嘘をつく。(偽物の満足を得、その場に留まり続けること)
- これを防ぐためには「仲間に関心を持ち、信じ、共感する。仲間の幸せや成長に役立とうとする信頼感や貢献感」つまりアドラー心理学のキーワードである「共同体感覚」をその人の中に育てなければならない。
- 「共同体感覚」とは「自分は他の人に貢献している」という主観的な感覚、そして「他の人にもお世話になっている」という感謝の気持ちをもつこと。
- 人から褒めてもらいたい、承認してもらいたいと考えるのではなく、「自分が他の人の役に立っているのだ」と自分だけが味わえるだけで十分と考える。
人間とは・・・
そして、もっと端的に要約すると
- 人は、「成長意欲を持ち、人間関係の中で自分の居場所を常に確認している」
- 人は、社会や組織の中で「貢献と感謝」でつながっている感覚が何よりも大切
のような人間観が持つことが重要であると思います。
人材定着のための取組み方針は・・・
次に、この人間観を持ったうえで、人材の定着、職場に従業員が定着し、組織と個人が成長するためには、会社側にどのような取り組みが必要なのか基本的な方向性を考察してみます。
- 面白い仕事、ワクワクする仕事、そして憧れの先輩をつくること
- 組織社会化の取組みを丁寧に行い、仲間意識を高めること
- 信頼される会社になること
これらの取組みに関しては、7月のオフィシャルブログに投稿した内容と同じになります。
ぜひ、7月のブログをご一読いただければ幸いです。