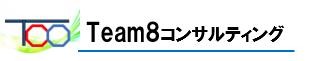「傾聴」だけでは「助言」は生まれない!
2021年8月8日『「傾聴」と「助言」との間で悩む!』というブログを投稿しました。
このブログの中で何らかの答えを求めてくる相談者に対し、「傾聴」に偏った面談を行っても相談者との信頼関係は築けないし、満足も得られない。逆に不満を抱かせてしまう可能性があることを述べました。
これはOSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センターに相談に来られる中小企業の経営者様や人事担当者様と面談をする中で感じていたことでもありました。
「求人を出しても応募がない」「求人を出しているが、なかなか採用ができない」だから、「どうすればよいか?」「OSAKAしごとフィールドではどんな支援をしてくれるか?」というのが主訴(しゅそ)となります。
支援者が、その主訴を横に置いておいて、「傾聴」「ヒアリング」にばかり時間をとっていると、相談者はイライラとされます。

「傾聴」で気を付けたいこと
相談者は、うまくいかなかった「経験」については、自ら進んで語ってくれますが、その結果を招いた「行動」については、あまり語ってくれません。
支援者にとっては、「行動」について事実関係を明確にしていく「傾聴」が必要です。しかし、勘違いしてうまくいかなかった「経験」ばかり「傾聴」し、共感していることが意外と多いと思います。
「経験」の「傾聴」「共感」は、ある程度の信頼関係が築ければ、それ以上の「傾聴」は必要がないと考えなければ、無駄に時間を要することとなります。
「傾聴」しないといけない、「共感」を伝えなければいけない、とばかり考えていると、相談者が求めている主訴に対する返答からは、遠ざかってしまう結果を招きます。
「助言」に必要なこと
これまでの私の経験の中で、「助言」をとても喜んでもらえた時、相談者の満足度が高かった時を振り返ってみると、いくつかの共通点があります。
- まず、主訴(相談者にとっての直接的な問題)に応えること
- これまで問題と思っていた相談者の視点や視座が変化していること
- 相談者が新たな行動を起こそうと思うような展望が開けつつあること
- 次にとるべき行動が明確になること
喜んでもらえる良い「助言」には上記のような要素が含まれている必要があると思います。
では、ここで問題意識が出てきます。
「傾聴」だけで良い「助言」が生まれるのかどうか?です。答えは、生まれない です。

勇気をもって「見立てる」
それでは良い「助言」のために、何が必要かについて、今、私が考えていることを述べたいと思います。
- 相談者の主訴を鵜呑みにするのではなく、問題を抱えている相談者の置かれている状況を捉え、理解に努める。
- 相談者の視界を妨げているものが何かを見つける。
- 経営理論やこれまでの事例、経験に照らし、相談者がどのような人間であるか勇気をもって「見立てる」(仮説を立てる)。
- 相談者が気づいていないであろう現実や事例を受け入れてもらえるかどうか、勇気をもって共感を求めていく(チャレンジする)。
- 相談者の潜在的能力や前向きな気持ちを信じ、その部分を見つけ、支援者の言葉で伝え、共感を求めていく(チャレンジする)。
- 今の状況に少しでも変化を起こせそうな具体的な行動の選択肢を2つから3つ提示してみる。
- 行動によって、新たな展望が開けることを具体的に伝え、共感を求めていく(チャレンジする)。
つまり、相談者には「勇気」であったり「チャレンジ」する気持ちが必要と思います。
上記に挙げた内容が、私にできているのかと問われると、まだまだできていないことが多いです。

カウンセリングに近い
経営相談は、ヒアリングやコーチングというよりも、カウンセリングに近いのではないかと最近、思うようになりました。
より多くの相談・面談を行い自らの面談内容を振り返ったり、多くの事例に触れたり、見本となる支援者を真似たりすることが上達の早道かと思います。
前月のブログでも述べましたが「鍛錬あるのみ」なのだと考えています。