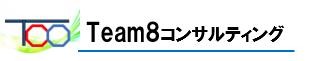研修がつなぐ「経営者の思い」と「現場の行動」
「研修講師」という新たな挑戦
今年も残すところ、あと2か月となりました。 経営者や人事担当者の皆様におかれましては、来期に向けた準備や今年度の総括など、慌ただしい日々をお過ごしのことと存じます。
さて、私自身にとっても、今年は非常に大きな挑戦の年となりました。それは、これまでの人事コンサルタントや中小企業診断士としての「助言・支援」業務に加え、「研修講師」という新たな役割に本格的に取り組む機会に恵まれたことです。

もちろん、これまでも人事制度の構築や運用支援の一環として、管理職向けの説明会やセミナー登壇の経験はありました。しかし、今年取り組んだのは、それらとは少し性質が異なる、従業員の皆様の「行動変容」を目的とした研修です。
なぜ、私が今、この「研修講師」という役割に力を注ごうと考えたのか。それは、これまでのコンサルティング活動の中で感じていた、ある種の課題意識がきっかけでした。
なぜ「助言」だけでは組織に浸透しないのか
私はこれまで、多くのクライアント企業様において、経営層の方々と共に人や組織に関する課題(特に人事評価制度や賃金制度、人材育成体系など)の解決に取り組んできました。
経営者の皆様は、会社の将来を真剣に考え、組織をより良くしようと強い情熱を持っておられます。その想いを形にするために、私たちは制度を設計し、運用のための助言や支援を行います。
しかし、どれだけ素晴らしい制度や方針を経営層と作り上げても、それが組織の末端、つまり現場で働く従業員一人ひとりにまで正しく浸透し、理解され、実行されているかというと、私自身、なかなかその手応えを実感できずにいました。
「おそらく、私たちが経営層と議論した内容やその背景にある『想い』は、そのままの熱量では組織に伝わらないのだろう」

そう感じる場面が少なくありませんでした。
当然のことながら、経営層の皆様は日々多忙を極めています。コンサルタントからの助言内容を組織全体に展開するには、まず経営者ご自身の言葉に変換し、次に中間管理職にその意図を理解させ、そして中間管理職を通じて従業員一人ひとりに伝えていく、というプロセスを経ることになります。
この伝言ゲームのようなプロセスの中で、当初の「想い」や「制度の本来の目的」が少しずつ薄まったり、あるいは解釈がズレて伝わってしまったりすることは、組織の規模に関わらず起こり得ることです。

この、経営層の「想い」と現場の「行動」の間にあるギャップを埋めるために、外部の支援者(コンサルタント)として何ができるか。従業員に直接語りかけ、理解を促す作業をお手伝いする方法はないか。
そう考えたとき、やはり最も有効な手段の一つは「社内での集合研修」ではないか、という結論に至ったのです。
研修講師として直面した「ギャップ」
ただ、研修を実施するにあたり、大きな懸念がありました。 それは、単なる「外部の講師」が話をするだけでは、従業員の皆様が本当に「聴く耳」を持ってくれるだろうか、ということです。
これまで私が行ってきたセミナー講師の仕事は、どちらかというと一方的な情報提供の側面が強いものでした。「人事担当者の皆様は、きっとこのような情報が知りたいのではないか」と私なりに仮説を立て、知見をお話しするというスタイルです。
しかし、「研修講師」は違います。 研修のゴールは、受講者が知識を得ることではなく、研修後に職場での「行動変容」を起こすことにあります。そのためには、受講者の方々に「この講師の話は聴く価値がある」と信頼してもらわなければなりません。
具体的には、 「この講師は、我が社の実情や日々の業務の課題をよく理解している」 「この講師は、経営層が取り組もうとしていることの意図を、私たちに分かりやすく補ってくれようとしている」 「この講師は、私たちが(内心)苦手にしていることや、もっと学びたいと思っていることを理解した上で話をしてくれている」 このように感じてもらう必要があります。

この「信頼」を得ることは、日頃から社内にいる人間ではない、私のような外部コンサルタントにとっては非常に難しい課題です。
そして、今年一年、研修講師として現場に立たせていただく中で、改めて気づかされた最も重要なことがあります。 それは、研修をオーダーする経営層と、研修を受講する従業員との間にある「知識」「認知」「意識」のギャップがいかに大きいか、ということです。
経営層は「(できて当たり前だから)意識改革をしてほしい」と期待し、受講者は「(やり方が分からないから)具体的なノウハウを知りたい」と思っている。このギャップに気づかず、経営層の言葉だけを鵜呑(うの)みにして研修を進めてしまえば、受講者にとっては「また上から目線の精神論か」と受け取られ、行動変容どころか、かえって不信感を抱かせてしまいます。
研修中であっても、受講者の表情や発言、グループワークの様子を注意深く観察し、この「ギャップ」を常に意識しながら、使う言葉や説明の順序を調整していく。 経営層の「想い」と現場の「現実」を繋ぐ翻訳者としての役割こそが、コンサルタントが研修講師を務める最大の価値であると痛感させられた一年でした。
自律的な成長を支援する研修を目指して
人事分野の研修では、心理学や組織心理学の理論的な「フレームワーク」を活用することが多くあります。例えば、モチベーション理論やリーダーシップ理論、コミュニケーションのモデルなどです。
しかし、理論を理論として教えるだけでは、現場の行動には繋がりません。 大切なのは、それらの理論を「なぜ今、自分たちが学ぶ必要があるのか」という文脈で分かり易く説明し、「自分の職場で具体的にどのように活用できるか」を受講者自身に考えてもらうプロセスを設計することです。

私は、研修を「学びの場」であると同時に、「実験と検証の場」として機能させたいと考えています。 研修で得たフレームワークを使い、まずは職場で試してみる(実験)。そして、その結果どうだったかを振り返り(検証)、自分なりに改善点を見出す(内省)。
このサイクルを回すきっかけを提供し、受講者自身が「自律的」にスキルを高め、成長しているという自信を身につけてもらえるような、そのような研修ができる講師を目指したい。

今年度の研修講師としての経験と反省を踏まえ、来年度はさらに経営層の想いと現場の現実を繋ぐ「橋渡し役」として、研修講師としての実力を高めていきたいと考えております。 経営者の皆様、人事担当者の皆様も、もし「方針は示しているのに、現場の行動が変わらない」といったお悩みがあれば、一度「研修」というアプローチをご検討されてみてはいかがでしょうか。