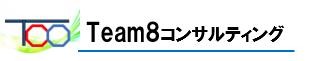フィードバックで内省力を育み、自律的成長を促す
なぜ今、フィードバックが育成の鍵なのか?
多くの中小企業で、管理職の方々が部下育成に頭を悩ませています。「年上の部下にどう接すればいいか分からない」「ハラスメントを恐れて、言うべきことを言えない」「プレイングマネージャーとして自分の業務に追われ、育成に時間を割けない」。このような声は、決して珍しいものではありません。従来の経験則に基づいた指導が通用しにくくなる中、育成の新たな武器として注目されているのが、科学的根拠に基づいた「フィードバック」の技術です。
立教大学の中原淳教授は、フィードバックを単なるコミュニケーション術ではなく、体系化された「技術」として捉え直すことを提唱しています。これは、精神論に頼るのではなく、具体的なステップとフレームワークを用いて、部下の成長を促すアプローチです。本日は、この中原教授の理論を参考にしながら、人材育成の本質について私の考えを述べさせていただきます。

経験学習を加速させる具体的な技術とは
中原教授の理論の根幹には、「経験学習サイクル」という考え方があります。これは、人が「経験」→「内省」→「概念化」→「実践」というサイクルを回すことで学習するというモデルです。多くの職場では、ただ経験を積ませる「経験至上主義」に陥りがちですが、経験を本当の学びに変えるためには、自らの行動を客観的に振り返る「内省」のプロセスが不可欠です。
フィードバックは、この「内省」を外部から効果的に促すための触媒、いわば「成長の鏡」としての役割を果たします。鏡がなければ自分の姿を客観視できないように、他者からの客観的なフィードバックがなければ、従業員は自らの行動やその影響を正確に認識することが難しいのです。

そのための具体的なツールが「SBIフレームワーク」です。これは、Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の3点から、事実を客観的に伝える手法です。「君はいつも遅い」といった主観的な評価ではなく、「先週金曜締切の報告書が(S)、月曜朝に提出されたことで(B)、部署全体の報告が遅れ、会議に影響が出た(I)」というように、具体的な事実を伝えることで、相手は行動を冷静に振り返ることができます。この客観的なデータに基づき、問題行動を改善する「是正的フィードバック」や、強みを伸ばす「ポジティブフィードバック」を行うことが、中原教授の提唱する技術の核心です。

技術の先に目指すべき、部下の内なる変化
このSBIフレームワークをはじめとする中原教授のメソッドは、非常に実践的で有効なものだと感じています。しかし、この優れた技術を実践する上で、私がさらに重要だと考えている視点があります。それは、フィードバックという対話を通して、相手をどのような状態に導くべきか、という点です。
私は、フィードバックを行う究極の目的は、単に行動を是正したり、強みを認識させたりすることだけではないと考えています。フィードバックを重ねる中で、相手自身が次の二つの力を身につけられるよう導くことが不可欠です。
一つ目は、「自らを客観的に見ることができる力」です。最初は上司という「鏡」を通して自身の姿を見ていた部下が、やがて自分の中に鏡を持ち、自らの言動を俯瞰的に捉えられるようになること。これが自律の第一歩です。
二つ目は、「内省の材料となる気づきを得る力」です。フィードバックは、答えを与える「ティーチング」とは異なります。対話を通じて、「なぜ自分はあの時、ああいう行動をとったのだろうか」「この経験から何を学べるだろうか」と、本人が自ら問いを立て、深く考えるきっかけを提供すること。この「気づき」こそが、内省を深め、持続的な成長の原動力となります。

対話を通じて、自律的に成長する組織へ
フィードバックの技術を正しく用いることは、部下育成において強力な武器となります。しかし、その技術は、部下の内面的な成長を促すという目的意識があってこそ、真価を発揮します。客観的な事実を伝え、対話を重ねる中で、部下が自らを客観視し、内省する力を育んでいく。このプロセスを支援することこそ、上司や人事担当者に求められる役割ではないでしょうか。
最初は時間のかかる、根気のいる取り組みかもしれません。しかし、従業員一人ひとりが自律的に学習し、成長する能力を身につけた時、それは組織全体の大きな力となります。中原教授の言葉を借りれば、個別の問題を解決するだけでなく、フィードバックが日常的に行われる「フィードバック文化」が組織に醸成されていくのです。

明日からの面談で、少しだけ「相手にどうなってほしいか」という視点を加えてみてください。その小さな意識の変化が、部下の、そして組織の未来を創る一歩となるはずです。