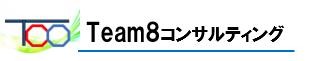人事管理の基本を押さえる(3)ー社員格付け制度ー
先月のブログでは「人事管理の基本を押さえる」の2回目として人事管理の基盤である「社員区分制度と社員格付け制度」の中の「社員区分制度」について説明しました。

今回は「人事管理の基本を押さえる」の3回目として人事管理の基盤である「社員区分制度と社員格付け制度」の中のもう一方の「社員格付け制度」について解説したいと思います。
社員区分制度の意義(再掲)
労働関係の法制度や世の中の労働市場の影響、そして労使関係からの要請を受けて、企業には多様な働き方が求められています。よって、企業の中には、仕事内容、働き方、キャリアの異なる多様な従業員が雇用されています。それにもかかわらず、ひとつの人事管理制度を全従業員に適用すれば、管理をするうえで、さまざまな問題点が出てきます。具体的には、正社員(営業・技術・製造・事務などの職種や総合職・専門職など)、契約社員、パートタイマーの賃金、手当、福利厚生、その他処遇の比較の問題です。「パートターム・有期雇用労働法」は、これまで以上に「なぜ、その賃金なのか」「なぜ、正社員と賃金が異なるのか」を非正社員に説明することを求めており、この「社員区分制度」が基盤としてないと、すべての説明が難しくなります。
社員格付け制度の意義
社員区分が決まると、その社員区分の中で社員の順位付けが必要になる。例えば、「正社員の営業職」という社員区分があるとします。では、何を基準に順位付けすればよいでしょうか?何を基準に地位を与えたり、給与・賞与の額を決めればよいでしょうか?
つまり、ここで「会社にとって重要な人」「経営目標を達成する(戦略実行)のために重要な人」のようなその会社にとっての「重要度の基準」が必要となってくるわけです。
この「重要度の基準」が「職種における重要度の基準」に展開される必要性につながってくるわけです。
この「会社にとっての重要な基準」に基づき社員を順位付けする制度を「社員格付け制度」といいます。
会社内の「役職(主任、係長、課長、部長など)の制度」は「社員格付け制度」とは別の制度であり、役職を決める上で「社員格付け制度」は基礎となっています。
社員格付け制度の多様性
さて、次は「会社にとっての重要な基準」を何にするかを決めなければなりませんが、下図に示すように多様な基準があります。この基準は、その会社の経営理念や経営戦略に大きな影響を受けます。また、その時代の労働市場の動向にも影響を受けます。

図表:「社員格付け基準と社員格付け制度の構成」を参考に筆者作成
大きく分類すると、【人】・【仕事】・【市場】の3つの視点があります。
【人】の長期の労働意欲を基準として採用したとき、そのひとの勤務姿勢や勤続年数を評価指標にした年功型人事制度を選択することとなります。
【人】の職務遂行能力を基準としたときは、職種ごとに職務遂行能力基準を定義し、その基準を満たしているのかどうかで、順位付けをしていきます。
この【人】視点の基準を採用する場合、その社員の将来性(将来価値)を重視した順位付けの制度になります。
【市場】視点の成果に基準を置いた場合は、売上、利益、生産性などが評価指標となり、実績(結果価値)を重視した制度となります。
事業部長などの市場責任を任されている社員に対しては使える制度になるかもしれませんが、上位の役職に就かない従業員を順位付けする基準としては、近視眼的となり、チームワークを必ずしも重視しない方向に従業員をリードする可能性があります。

【仕事】視点の基準は、今、ブームです。同一労働同一賃金、ジョブ型人事制度、転職市場や副業兼業市場の活性化など影響を受けていると考えられます。この基準は、その人の「現在価値」を評価し、それに対してしっかり処遇していくという制度です。代表的なものに「期待役割等級制度」や「職務分類(ジョブ型)制度」があります。
社員格付け基準の選択と組合せは企業の戦略そのもの
ここまでお読みいただければ、社員格付け制度における「基準」の選択と組合せは、その企業にとって「何を大切にするか」そのものであることがわかります。
そしてこの「基準」は、社員に対する明確なメッセージになることも容易に想像がつきます。
例えば、ある経営層が経営目標を明確に定め、戦略実行のために必要な基準は「勤続年数」要素が3割と「その職務での期待役割」要素が残り7割と決めたとすれば、社員に対し、その基準を明文化し、はっきりと示すことが重要です。
社員は、経営層の考え方に賛同した場合、その基準を満たすために自己研鑽するからです。
中小企業の場合、社員格付け基準が明文化されていないことが多いと思いますが、社長の頭の中にははっきりと基準があります。明文化することは、とても時間と手間がかかる作業ですが、企業の戦略と社員の成長に直結することなので大切にしていただきたいと思います。
このブログが、中小企業の人事制度の整備に少しでも役に立てばと思っています。ご不明点があれば何なりと問い合わせください。