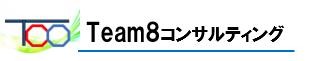ヒアリング技術の向上は鍛錬あるのみ!
最近、クライアントに対しヒアリングの機会が多くありました。
会社に勤めていた時も、営業職であったので「顧客の要望をしっかりと聴きとる」「顧客の抱えている課題を整理し聞き出す」について30年近く経験をしてきました。よってヒアリングについては相当練習をしてきたと考えてもよいと思います。
自分でも気づいていない言葉癖
先日、私が初対面のクライアントに対してヒアリングしているところを、第三者に立ち会ってもらい、ヒアリング内容について振り返り(フィードバック)をしてもらいました。
自分でも気が付いていないことが多く、指摘を受けると恥ずかしいことが多くありました。
いくつか挙げますと
- 言葉が丁寧すぎて質問が長くなる
- 質問の趣旨がはっきりせず、質問を継ぎ足してしまうので、クライアントは答えにくくなる
- オープンクエスチョンが多く、そのオープン度合いも大きいのでクライアントは答えにくくなる
- 「なるほど」という相づちが多い 「なるほど」は使わない方がよい
- 「なぜ」を使いすぎると、クライアントは困った感じになる
- 質問の答えが待てず、質問の継ぎ足しをしてしまう
のような内容です。

「相づち」には気を付けよう
特に気を付けたいと思うことがあります。
「相づち」です。
つい最近、radiko(ラジコ)でFM放送を聞いていて、ゲストに対するインタビューの中で、その「相づち」がとても気になったことがありました。「はい、はい、はい」・・・「はい、はい、はい」・・・「はい、はい、はい」という「相づち」です。とても聞き苦しかったです。プロでも、このような悪い言葉癖を直すことができないだと驚きました。
コンサル業界の中でも「なるほど」という「相づち」は、なるべく使わない方が良いと言われています。
我々は、経営者(創業者)から、経営にかかわるお話をお聴きするのですから、「なるほど、なるほど」と「相づち」を打ってしまうことは、経営者(創業者)に対し、不快感を与えると言われています。
「あなたは、本当にこのこと(苦労や考え方など)が理解できているのですか?」と不信感を抱く可能性があるのです。
「相づち」は必要最低限でよいのだと気づかされますし、相手のお話し(苦労や考え方)を誠実に受け止める姿勢が大切であるということもわかります。
アイビイが体系化したカウンセリング技法
1985年にアイビイの著した「マイクロカウンセリング」(川嶋書店)でカウンセリングの技法が体系化されました。カウンセリングを必要とする方々のバイブルのような書籍です。キャリアコンサルタントなどもキャリアカウンセリングの支援スキルとしてこの理論を学びます。
さきほどの「相づち」は、本書の中では「基本的かかわり技法」の中の「かかわり行動」の「言語追跡」に当たります。あくまでも「傾聴」の姿勢を保つための行動であるべきという説明です。
「かかわり行動」の中には、「視線」「身体言語」「声の調子」そして「言語追跡(=相づち)」の4つがあります。詳しく知りたい方は、「マイクロカウンセリング」アイビイ著(川嶋書店)をご参照ください。

鍛錬あるのみ
ヒアリングのスキルを上げるためには、理論を理解し、その理論を意識しながら実践で使ってみる、録音した自分のヒアリング内容を聞き直し、ダメ出しをして改善点を書き出す。
この繰り返ししか無いように思います。第三者に評価してもらうことも良いと思います。
ヒアリングのスキルは、コンサルティングの仕事において、基本中の基本です。今後も意識して取り組んでいこうと思います。