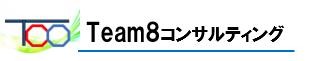成人発達理論は人材育成に活用できるか?
今回も私が今関心を持ち、自分なりに理解を深めようとしているテーマをブログを通じてご紹介させていただきます。まずは、2冊の書籍に出会うことができました。
- 「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法 – 2024/2/28オットー・ラスキー (著), 加藤 洋平 (翻訳), 中土井 僚 (翻訳)
- 組織も人も変わることができる! なぜ部下とうまくいかないのか 「自他変革」の発達心理学 – 2016/3/24加藤 洋平 (著)
の2冊です。この本を知るきっかけは、動画サイトの中で加藤洋平氏の対談動画を視聴し、心理学の中に「成人発達理論」という研究があるということを知り、まず『「人の器」を測るとはどういうことか』を読み始めましたが難しくて理解ができなかったので、『組織も人も変わることができる! なぜ部下とうまくいかないのか』を先に読んでから、再度チャレンジしたという経緯があります。

成人発達理論とは
成人の心の成長の過程を明らかにしようとする学問領域です。この書籍では主にハーバード大学のロバートキーガン教授の成人発達モデルを参考にしています。
大人になってから生涯を終えるまで、人間は心の成長をしていくわけですが、その心の成長は、階段になっており、階段を1段上がることができれば、認知できるものが大きく変わってくる(他者の捉え方、欲求、自己洞察、価値観が変わる)ということを研究している学問領域です。
また、その発達段階を測定するための手法(インタビュー手法と分析方法)も実証研究されておりこの本では、成人の発達段階は発達段階2から始まり発達段階5まであると説明されています。
発達段階とは具体的にどのようなものか?
下に発達段階2、3、4、5の概要を示します。
この表は「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法 – 2024/2/28オットー・ラスキー (著), 加藤 洋平 (翻訳), 中土井 僚 (翻訳)の中に掲載されている表を参考に私が作成したものです。

発達段階2 道具主義的段階(利己的段階)
- 自分の関心事項や欲求を満たすことに焦点が当てられる
- 自らの関心事項や欲求を満たすために、他者を道具のようにみなすという意味から「道具主義的」と形容される
- 他者の感情や思考を理解することが困難
- 他者の視点も考慮し始める、次の発達段階3への移行のサインとなる
発達段階3 他者依存段階(慣習的段階)
- 組織や集団に従属し、他者に依存する形で意思決定する
- 自らの意思決定基準を持っておらず「会社の決まりではこうなっているから」「上司がこういったから」という言葉を多用する傾向がある
- 他者(組織や社会を含む)の基準によって、自分の行動が規定されている
発達段階4 自己主導段階(自己著述段階)
- ようやく自分なりの価値観や意思決定基準を設けることができ、自律的に行動できる
- 段階3では、行動基準が周りの存在によって築き上げられていたのに対し、段階4は、自らの行動基準を構築することができる
- 自己成長に強い関心があったり、自分の意見を明確に主張したりする特徴がある
発達段階5 自己変容・相互発達段階
- 自分の価値観や意見に囚われることなく、多様な価値観・意見などを汲み取りながら的確に意思決定ができる
- 段階4は、自らの成長に強い関心を示していたが、段階5は他者の成長に意識が向いている
- 他者が成長することによって、自らも成長するという意識(相互発達)があり、他者と価値観や意見を共有し合いながら、コミュニケーションを図る特徴がある

発達段階を何で見分けるのか?
書籍の中で、この発達段階をどう測定するかについても説明されています。
しかし、とても理解しにくいので私の理解と解釈によりますが図にしてみました。

書籍にも出てくるハーバード大学 ロバートキーガン氏の言葉として、「人間は生きている意味を構築することを宿命づけられた生き物である。人間は意味構築活動を常におこなっている。意味構築は意味構築装置によって行われる。意味構築装置の機能は発達段階によって変わる。」と紹介されています。
つまり、私であれば、【外の世界・他者】と【自己】の両方を私の心の発達段階による意味づけ【意味構築活動】によって【言語化】されます。その言語化に発達段階の違いが現れるのだそうです。
そして、その【言語化】についても、話の内容ではなく、「どのような言葉を使い、どのように使うか」に着目することにより、「他者の捉え方」「欲求」「自己洞察」「支配欲」「価値観」「コミュニケーション」に、その発達段階に応じた特徴がみられるという説明です。
書籍には、その測定のインタビュー事例などもたくさん紹介されていますのでご興味のある方はぜひ本を手に取ってください。
成人発達理論のフレームワークは、人材育成に活用できるのか?

私は、人材育成に活用できるのではないか、自分の人事分野のコンサルティングに活用することができないかという期待から、現在も知見を深めようとしていますし、クライアントに対して成人発達理論のフレームワークを紹介して、感想や考えを聴くようにしています。
私なりの考えを述べたいと思います。
- 自分自身の心の成長について内省するきっかけとなる
- 組織の中でメンバーとやり取りが上手くいかない時
- 感情的にならずに、冷静に対処できる
- 人材育成のアプローチに仮説検証的手法を取り入れることが可能
このような効果があるのではないかと考えていますので、この理論的フレームワークをわかりやすく説明でき、活用可能なツールにできれば良いと考えています。
但し、活用における注意点もあると感じています。それは
- どの発達段階も組織には必要であることを認識すべきである
- 発達段階の判定は専門家しかできない。安易に他者の発達段階を決めつけたり、そのことを他言してはいけない。
と思います。
私が日頃仕事にしている人事領域では、成人発達理論の活用事例はあまり聞きませんが、人間の本質的テーマでもありますので、引き続き知見を深めていきたいと考えています。