採用できている企業と採用できていない企業の差 募集編(2)
2024年3月8日のオフィシャルブログ「採用できている企業と採用できていない企業の差(1)」の続きを投稿します。
このブログだけを読んでも、流れがわかりませんのでお手数ですが、下記のリンクから前回ブログをお読みいただければ幸いです。
2024年3月8日のオフィシャルブログ「採用できている企業と採用できていない企業の差(1)」
前回のオフィシャルブログでは
- 採用力診断ツールとは何か
- 採用力診断ツールのコンセプト
- 診断項目の詳細
について解説しています。

統計的分析の方法 t-検定:2つの標本(平均値)に有意差が認められるかの分析
採用力診断の20設問ごとに、採用成功企業の平均値と採用不成功企業の平均値との間に有意な差が認められるかを確認するのが適当と考え、t-検定(分散が等しくないと仮定した2標本による検定)による統計的分析を行いました。
t-検定は、Excelで簡単に分析することができます。
t-検定とは、簡単に説明すると、2つの標本、ここでは採用成功企業405社と採用不成功企業1175社の2つのグループの平均値の差に有意な差があるかどうか判定し、一定の結論を出そうとする分析手法です。
「有意な差」とは、確率論的に、たまたま出た差ではなく、「意味のある差」である可能性が高いということです。個々の分析では、その「たまたま出た差」が出る確率が5%以下であれば「有意な差」があると判定しています。
t-検定についてご存じでない方もいらっしゃると思いますが、YouTubeで解説動画がたくさんアップされていますので、自習していただければと思います。私は、田中嘉博さんの「【実践編①】t検定:難しい数式と専門用語を使わない統計学シリーズ」を視聴し勉強させていただきました。
「募集」t-検定の結果 平均値に有意な差があったのは「自社の魅力把握」のみ

「募集」の5つ質問の詳細は、冒頭で述べた前回のオフィシャルブログでご確認頂きたいのですが、質問項目は「自社の魅力把握」「自社の魅力発信」「求人媒体の活用」「イベントの活用」「職場環境」の5つです。
採用に関わる「募集」のフェーズにおいて、私は重要な取組み項目であると考えていた「自社の魅力把握」「自社の魅力発信」「求人媒体の活用」「イベントの活用」「職場環境」の中で、採用できている企業と採用できていない企業の差として、「意味のある差」は「自社の魅力把握」だけであるという検定結果がでました。
「自社の魅力把握」の採用成功企業405社と採用不成功企業1175社の2つのグループの平均値の差において、「たまたま出た差」が出る確率が0.09%で検定基準としている5%よりも圧倒的に小さいことがわかりました。明らかに、この差は意味のある差であるということです。
ちなみに他の質問項目ではどうかと言いますと「自社の魅力発信」69%、「求人媒体の活用」87%、「イベントの活用」41%、「職場環境」14%であり、「たまたま出た差」が出る確率が5%よりも相当高いという結果がでました。

採用活動で「自社の魅力把握」にどれだけの手間をかけているか振り返ってみてください
「 自社の魅力把握 」について、 自社の強みや魅力について、従業員へのインタビューや社外関係者への
アンケート等を用いて客観的に分析し、把握している。(最も当てはまるものを、単一回答)
1: 自社の魅力を把握していない
2: 魅力だと認識していることはあるが、インタビューやアンケートに基づいた分析はしていない
3: 魅力を分析し、把握している
4: 魅力を把握しており、応募者に伝える際に有効活用できている
採用活動で期待する成果が得られていない会社の経営層及び人事責任者の皆さまは、上記質問をぜひ振り返っていただきたいと思います。ウチの会社には魅力はないとあきらめている方もいらっしゃると思いますが、会社の創業から現在までの歴史(沿革)の中に魅力のヒントが隠れています。金融機関や公的機関(OSAKAしごとフィールドなど)に相談し、第三者の意見もぜひ参考にしてください。そして、求職者に魅力を伝えるための言葉選びにもこだわっていただきたいと思います。
次回は「選考」フェーズにおける、t-検定の結果について投稿します。
投稿が待てない方がいらっしゃればOSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センターにお問い合わせください。
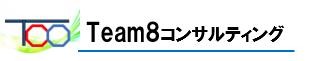
“採用できている企業と採用できていない企業の差 募集編(2)” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。