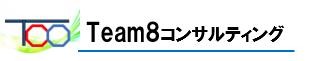「ビジョンの共有」ってよく言いますが、難しくないですか?
「ビジョンの共有」「経営理念の共有」など、ビジネスの現場にいると、よく聞こえてくる言葉です。自分自身も、職業上よく使う言葉ですし、組織が活性化するためには必要なことと思います。
先日、中小企業が100社程度集まった合同企業説明会の運営のお手伝いをする機会がありました。
求職者として新卒者、既卒者、転職希望者、外国人の方など多様なバックグラウンドを持つ方々が約600人来場されて、それぞれご自身の興味のある企業ブースを訪問して、一生懸命に説明を聴いたり、質問をしたりされていました。
その中で、出展されている企業のご担当者の方が、求職者に対して次のようなお話しをされていました。
「経営理念、経営ビジョンに共感し、共有していただける人でないと、すぐに離職されてしまいます。そのことをご理解いただき応募していただきたいのです。」
この言葉は、間違ってはいないと思いますが、私は違和感を感じました。

まったく共感できない経営理念やビジョンなど、あるのだろうか?
- 少なくとも20年以上存続してきた中小企業の経営理念に共感できない人などいるのだろうか?
- 経営理念や経営ビジョンについて、その会社に入社する前から共有することはできるのか?
- 離職理由は、もっと他にあるのではないか?
話は変わります。私事を振り返ってみました。
私も会社員を31年間続けておりました。その会社の経営理念は「産業人たるの本分に徹し 社会生活の改善と向上を図り 世界文化の進展に寄与せんことを期す」というもので、当時は、雲の上の方の「おことば」で、共感はできますし、創業者の時代背景を理解しつつ、共有もしておりました。
しかし、その共感や共有は、自らの日々の仕事をするために、なくてはならないものか?と言えば、そこまでのものではない。自分の仕事に対するモチベーションを高めているものか?と言えば、そんなことはありませんでした。
だからと言って、経営理念やビジョンに共感していないかと言えば、それに敬意を払っているし、「確かにその通りだな」と思っていました。
だから、経営理念やビジョンを外部の方々に、いきなり共感してもらうことは大変難しいことではないかと思っています。
なぜ、自分に響かないのか?
では、なぜ自分に響かないのでしょうか?
それは、「自分ごとになっていない」からだと思います。
「他人のよいお話」「自分には直接関係ない」と思っているから自分に響かないのだと思います。

ビジョンの共有には順序がある?
組織が活き活きする、自分が前向きになる「ビジョンの共有」には順序があるのではないでしょうか?
まずは、自分が何に憧れをもち、どんな自分になりたいと思っているのか内省が必要ではないでしょうか?
つまり「私のビジョン(志)」です。
これは、その人が何を志し、何に取組み、どのような経験を重ね知見を深めてきたかによるでしょう。
新卒で入社した会社で無理をし、心と体のバランスを崩して一時的に社会から離脱したが、再度、就業を志そうとしている方には、その方なりのビジョン(志)があると思います。
自分の親が事業に失敗し、家族が路頭に迷うような経験をした若者がいたとしてら、先ほどの方とは別のビジョン(志)があると思います。
組織のビジョンと擦り合わせたり、重ね合わせたり
次のステップとしては、組織が掲げているビジョンと自分のビジョン(志)とを、擦り合わせたり、重ねたりする必要があると思います。特に経営層と対話を重ねながら、自分のビジョン(志)と共通点があるか、そして、経営層がそれを本気で実現しようとしているのかを感じ取ることが大切であると思います。
経営層や組織責任者との対話ができない場合は、自分のビジョン(志)と一致する部分が本物かどうか、若い従業員や取引先の話を集め、エビデンスとし、信頼できるかどうかを検証する必要があります。
このようなプロセスを経て、初めて「ビジョンの共有」ができるのではないかと思っています。

採用担当者は求職者に対し経営理念やビジョンをどう伝えるべきか?
冒頭の合同企業説明会に出展していた採用担当者は、求職者に対しどのようなメッセージを送るべきだったのでしょうか?
私であれば・・・
経営理念やビジョンが生まれた背景や創業者の体験を語ります。
そして、当社ブースを訪れた求職者のビジョン(志)と擦り合わせることによって、自分ごとに置き換えることができそうかどうかを尋ねると思います。
重なる部分が見つかれば、とてもラッキーなことだと思いますし、大切にすべきことだと思います。