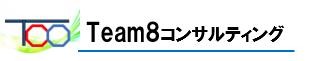「社員の幸せ」を経営の目的にすると何が起こるか
5月19日(土)に長野県伊那市にある伊那食品工業株式会社に視察に行ってきました。枚方信用金庫様がこの視察の機会をつくってくださいました。
当日はあいにくの雨でしたが、本社の広大な敷地の中に一般公開されている「かんてんぱぱガーデン」の見学やガーデン内レストランで地元食材をふんだんに使ったお弁当を食し、その後は綺麗な講堂に案内されました。
講堂の中はセミナー会場になっており、これまでもたくさんの見学者や視察団が、伊那食品工業の経営理念を学びに来ているのだと思いました。
小口常務取締役のお話を、約1時間、拝聴することができ、感銘を受けたあの時の感覚を今でも思い出すことができます。

社員は「家族」である
伊那食品工業は、資本金9,680万円。年商200億円、従業員数は520人を超える。このような企業のトップが「社員は『家族』である」と言い切る。
家族は、みんなで力を合わせて、みんなで幸せになる。そのためには年功を大切にし、それぞれが活躍する場を大切にしている。会社は「家族」をめざしている、家族となり、幸せになるための人事制度や福利厚生、職場環境(事業所内、敷地内の心地よい環境)を準備し、毎年少しづつ充実させている。
経営の目的は「社員の幸せ」である
経営の目的は、顧客への価値提供や満足ではなく、「社員の幸せ」であると断言する。さらに、会社の売上や利益は「社員が幸せになる」ための手段であるという。
利益に対する考え方も、一般的な経営者と大きく異なる。「利益」とは会社の「ウンチ」と表現している。人間も健康体であればお通じがあるように、会社も「健康な経営体」であれば「利益」は自然に出てくると。よって、「利益」の最大化を目的にする経営は根本的に考え方がおかしく、「利益」は、健康な会社をつくるための手段にすぎないと説明している。
また、業績の急成長や企業規模の急な拡大は必要ないという。急成長は会社のためにならず、弊害の方が多いともいう。
その理由は、少しづつ成長すれば、大きな設備投資は必要なく、従業員への投資(昇給や福利厚生)に回すことができるからだ。

社員は会社の思いに応えてくれる
一貫して、「社員の幸せ」のために経営をしていると、自然と社員は会社の思いに応えてくれる。会社に対して貢献したい気持ちなってくれる。
少しづつ成長するために、昨年度より、頑張ろうという気持ちになる。
寒天という自社商品の用途開発の幅を広げるために、研究開発に社員全員の関心が向く、社員同士のコミュニケーションが深まり、新規顧客の開拓が行われる。このような好循環がバランスよくいろいろな部門で起こるそうです。
最も生産性が上がるのは、設備投資ではなく社員のやる気
誰もが気がついていると思いますが、会社組織が人で構成されているのであれば、社員全員のやる気が高まることが、最高の生産性向上策と言えます。人が自分の働く目的に気づき、自分で考え、選択した仕事であれば一生懸命に働くでしょう。さらに、みんなで一緒に会社に恩返しし、一緒に豊かな人生を送ろうと考えていればさらに良い仕事ができるのではないでしょうか。
この経営理念は、どんな企業でも取り入れることができる
他の中小企業の社長が、この話を聴けば、「ウチのような会社で、そんな取組みをしたら会社が倒産してしまう」と考えてしまうかもしれません。
伊那食品工業株式会社の創業者である塚越最高顧問も、伊那食品工業の社長代行として経営を任されたときは、21歳で、会社規模も小さく家内工業のような体であったと言っています。
貧乏会社で労働環境も悪く、給与も低い会社に、「どうやったら人が来てくれるか」「どうやったら人が定着してくれるか」「会社の魅力を少しでも高めるにはどうすればよいか」「作業環境、職場環境を少しでも良くしてあげるためには何をすればよいか」これらのことを徹底的に考えていたそうです。
このような経営者の思いが、会社の中で少しずつ実現して形になり、さらに、社員に対し感謝、ねぎらい、思いやりのある言葉をかけることで信頼関係が生まれてきたとおっしゃっています。
よって、立派に聞こえる経営理念や社是は、昔から社長が考え続けてきたこと、社員に伝えてきたことが明文化されたのだとわかります。
普段、職場で社員に対して話したことがないようなことを、経営理念や社是、行動指針としてかっこよく明文化したところで、せいぜい社員から冷めた目で見られるのが関の山でしょう。
今からでも遅くはない。「社員の幸せ」のために経営することは、今この瞬間からでも取り組めることであると思う。