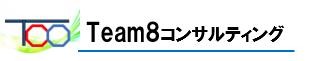「組織開発」について学び直しました
3月に南山大学人文学部心理人間学科教授の中村和彦氏の講演を聴く機会があり、支援の在り方について解説されている中で、組織に対する関わり方にプロセスコンサルテーションという手法があると話されていました。大変、興味深いお話であったため、自分なりに調べ始めると「組織開発」という学問のジャンルであることがわかりました。
今回のブログでは「組織開発」について述べてみたいと思います。
「組織開発」とは
組織開発はアメリカで1950年代終盤に生まれ、欧米を中心に発展してきたアプローチで「Organization Development」の訳語です。「開発」という言葉が使われていますが、Developmentには、「発達」「成長」という意味もあるので、組織開発とは「組織の発達、成長を促す」ものと理解すれば良いと思います。
日本では1960年代にQCサークル、小集団活動として企業に取り入れられ、徐々に浸透したようです。 その後、1970年代前半~1980年頃に最初の組織開発ブームあったと言われています。
最近では、2015年に「入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる」(中村和彦著 光文社)や2020年には「『データと対話』で職場を変える技術 サーベイ・フィードバック入門 これからの組織開発の教科書」(中原淳著 PHP出版)が出版されています。また、2011年に日本語訳が出た「学習する組織 システム思考で未来を創造する」(ピーター・M・センゲ著 英治出版)も組織開発に関係する知見がたくさん含まれているのではないでしょうか。

「組織開発」が注目されている背景
「入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる」(中村和彦著 光文社)で、日本の組織の現代的課題が説明されています。著書を参考にしながらポイントを挙げます。
①活き活きとできない社員
2007年第8回世界青年意識調査で、18歳から24歳の青年に対し、日本、韓国、アメリカ、イギリス、フランスの5か国に対して、「あなたは職場生活に満足しているか?」という質問に対し、日本が欧米と比べて満足度が低いという結果が出ている。
②利益偏重主義
今の上司が部下をマネジメントする手段として、売上高、利益やその他KPIなど、客観的で、数値で測定できるものを目標として伝え、その進捗状況を報告させるような上司にとって楽なコミュニケーションに偏っているのではないか。
③個業化する仕事の仕方
IT化の進展、テレワークの普及により非同期コミュニケーションが主流になることで、役割分担ばかりが進み、上司から部下への一方的な指示が増えて、さらに一人で仕事をする機会が増える。
④多様性の増大
アメリカほどの人種や性別、宗教、価値観の多様性はありませんが、日本においても、Z世代、若年層、高年齢者、外国人、女性、正社員、契約社員、パート社員、派遣社員、副業・兼業者など働く人の多様性と仕事に対する価値観が異なる人が共に働くことが増えてきました。
このような背景の中、職場をどのようにマネジメントすることが、組織の目標達成に効果があるのか、また、働く人々が前向きに、活き活き働くことができるのかが大きな経営課題とされています。
「組織開発」のアプローチ
組織の2つの側面
組織のマネジメントとは、「集まった人々を活かし、組織の目的を果たすことに向けて対処し、働きかけていくこと」と「入門 組織開発」の著者 中村和彦氏は述べています。
組織には「ハードな側面=形があるものや明文化されたもの」と「ソフトな側面=人の意識、モチベーション、思い込みや前提、コミュニケーションの仕方、協働性や信頼関係、お互いの影響関係やリーダーシップ、組織文化や風土など刻々と変化し、目には見えないもの」があります。
組織の6つのマネジメント課題
そして、ハードな側面のマネジメント課題は4つ「戦略」「組織構造」「制度」「技術・業務プロセス」があり、ソフトな側面のマネジメント課題は2つ「人(スキル・感情・健康)」「関係性(部門内・部門間・全社)」があると「入門 組織開発 中村和彦著」では説明されています。

「組織開発」がアプローチするのは「人」と「関係性」
「組織開発」がアプローチするのは、ソフトな側面の「人」と「関係性」に対してです。
つまり、形のあるものではなく、目に見えないものに働きかけて、組織目標の達成に貢献するというアプローチです。このことは「氷山モデル」で説明されます。氷山のように目に見えている部分は、ほんの一部分で、海面より下の見えない部分が「人(スキル・感情・健康)」「関係性(部門内・部門間・全社)」であり、そこに働きかけていくことが「組織開発」であるということです。
氷山の一番深い下の部分は、人の固定観念や認知バイアス、思考の偏りと言われており、対策の一例ですが、立場の違く方々と深い対話を繰り返すことによって変化していくとされています。

ここであらためて「組織開発」の定義
「組織開発」の定義は「組織の健全さ、効果性、自己革新力を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」(入門 組織開発 中村和彦著 光文社 より引用)
組織開発の手法(例)
組織開発の手法には、個人レベル、チーム/グループレベル、全社レベルと各レベルに応じて様々な手法があります。チーム/グループレベルでは、研修の形態をとって、ファシリテーター主導でワークショップを開催することが多いと思います。日本生まれの組織開発手法もあります。製造業を中心に行われた品質向上のためのQCサークルやTQCがそうです。オフサイトミーティングもそうです。
私が今注目をしているのは「サーベイ・フィードバック」という手法です。
このサーベイ・フィードバックという手法は、「『データと対話』で職場を変える技術 サーベイ・フィードバック入門 これからの組織開発の教科書」(中原淳著 PHP出版)で詳しく、そしてわかりやすく説明されていますので、ぜひご一読いただきたいと思います。
サーベイ・フィードバックとは
サーベイ・フィードバックとは、「サーベイ(組織調査)」で得られた「データ」を適切に現場に届け(フィードバックし)、現場の変化・職場の改善を導く技術のことです。※「『データと対話』で職場を変える技術 サーベイ・フィードバック入門 これからの組織開発の教科書」(中原淳著 PHP出版)P7を引用
最近では、HRテック企業がサーベイ(組織調査)の仕組みをクラウドシステムで提供し、そこから集計、分析、出力されるレポートを組織のリーダーに提供し、対話の材料とすることができるようです。
人事部門に組織開発専属スタッフを配置し、現場部門をサポートすることができる大企業では、取り組みも容易ですが、人員が割けない中小企業においては、なかなかハードルの高い取り組みとなります。

中小企業にも組織開発は必要か?
中小企業は、新商品・新サービスの開発、販路の開拓、付加価値の向上(差別化)、生産性の向上、品質の向上などの目標達成のために組織が活性化しているか?また、従業員が活き活きと前向きに働いているか?
そこに改善の余地や取組み課題があるのであれば、どのような組織開発のアプローチが良いか?
このことが、中小企業支援者としての私の課題です。
- 組織の効果性と健全性を測定するためのアンケート(質問)項目の検討
- そのアンケートをどのように集計し、組織の状態を見える化するか?
- 組織の状態の見える化レポートを利用し、どのようなチームでの対話ができるか?
- 支援者のファシリテーションスキルの向上
- そのファシリテーションスキルを中小企業の担当者に、どう伝えていくか?
を検討しています。
現在、この手法をカタチにするために協力していただける中小企業様を探しております。
とてもハードルが高い取組みであるとは思いますが、この取組みが動き出すと中小企業の業績に大きく影響を与えるのではないかと考えています。
もし、ご興味があれば、気軽にご連絡ください。詳しくご説明させていただきます。
以上 よろしくお願いします。